準備中
試用中です、しばらくお待ちください。
-
アーカイブ:詳細の上映会 年を選ぶ [年]
-
アーカイブ
トップ -
前へ
. -
2025
. - 2023
-2024 -
2021
-2022 -
2018
-2020 -
2015
-2017 -
2012
-2014 -
2009
-2011 -
2005
-2008 -
次へ
.
アーカイブ:詳細 2023年~2024年
第329回『噓八百 京町ロワイヤル』 ●上映日:2024年12月 蕨市民会館
第328回『世界で一番しあわせな食堂』 ●上映日:2024年12月 埼玉会館

ゲスト:谷口美帆さん(野菜ソムリエPro/食育マイスター)
テーマ:自分のしあわせな食卓って?
12月13日(金)「世界で一番しあわせな食堂」アフターセミナーを開催しました。
コミュニティセンター等でお料理教室を開いたり、月に3日程南区のヘルシーカフェのらでランチを提供している谷口さん。そんな食の専門家からこの映画はどう見えたのでしょうか?
フィンランドのお料理の特徴、どんなものが食べられているのか、どんな味付けか。映画の中にも出てきたソーセージは動物のお肉を無駄なく食べる先人の知恵であること。伝統を大切にしていること等を紹介してくれました。そして中国の料理人であるチェンの言葉で「バランスを重視する」というのが印象に残っていて、そのバランスとは味・色・効能・盛り付けまでを指すのだそうです。
精神の安定をもたらすお料理や元気を促進するお料理の簡単なレシピにも触れてくれました。医食同源という考え方は日本にも通じるものがありますね。
そんな谷口さんがお料理の道に進んだきっかけや最近感じた食の大切さを、ご家族とのエピソードを交えてお話くださり「食べる」という行為は生命力そのものなのだと実感したそうです。
この日のテーマである「しあわせな食卓」については7つの提案をして下さいました。
①誰かのために作る(一緒に作る)
②作る事を楽しむ
③食材の栄養や料理のルーツなどを勉強する
④お気に入りの器や道具を使う
⑤お気に入りの店や農家さんから買う
⑥お気に入りのカフェを見つけて自由を楽しむ
⑦最後に無理をしないこと!
食を通じて人と人が繋がっていくことで幸せが生まれるのをこの映画は描いているということ、谷口さんにとって「食卓を作ることはしあわせを作ること」そんなお話でまとめて下さいました。
会場の皆様にはお土産として野菜の重ね煮のレシピをお持ち帰り頂きましたよ。
第327回『ウィ・シェフ』 ●上映日:2024年12月 彩の国さいたま芸術劇場

ゲスト:寺中誠さん(東京経済大学客員教授)
2024年12月7日『ウィ、シェフ!』のアフターセミナーを開催しました。
アムネスティ・インターナショナル日本の元事務局長であり犯罪学・国際人権法等の専門家の立場からこの作品についてお話をしていただきました。
この作品は、タイトルやポスター等からわかるように、フレンチレストランやフランス料理がテーマのひとつとなっています。と同時に、フレンチ料理のスーシェフ(副料理長)だった女性主人公と移民の少年たちの交流が描かれていて、現在のフランスの移民政策の一端が伺える内容となっています。
寺中さんによれば、この作品の少年たちはおそらく移民一世であるとのこと。そして移民と犯罪の関係について「一般に移民一世の犯罪率は現地出身者より低い。何故なら移民先の国に受け入れてもらいたい溶け込みたい、という思いで来る人が多いから」と解説。しかしながら、現地の住民からすれば、「移民の数の増加は不安感を増幅させている。移民の二世以降は、移民か否かという問題ではなく生育環境の優劣に影響される」とデータ等を示しながらお話をしていただきました。
この作品は、フランスの伝統料理の料理人女性キャティが主人公です。彼女は移民の少年たちの自立支援のために伝統料理を教える立場として描かれていて、一見、フランス人と移民の少年たちとの間に差別偏見のない作品のようにみえますが、寺中さんによれば、この設定自体にがっちりとしたヒエラルキー(白人?フランス?至上主義)があることを指摘。一方で、主人公が実は施設出身でフランス社会でも恵まれた出自の白人ではないという説明を付け加えていることも製作者側の思いがあるのではないかとお話しされました。
また、寺中さんはこの作品を語るうえで“カミュ=サルトル論争”や“植民地主義”等にも触れ、現代のフランス社会が抱える問題などについても話は広がり、参加者のみなさんは熱心に耳を傾けていました。
今回は、上映期間中多くの来場者から、“よかった~!”と声をかけてもらえるほど満足度の高い作品でした。と同時に、フランス社会の矛盾や移民の問題等、私たちの住む地域にも関係するテーマがいくつも含まれている作品、ということを寺中さんのお話は私たちに気づかせてくれたように思います。
第326回『高野豆腐店の春』 ●上映日:2024年11月 草加市文化会館
第325回『シェアの法則』 ●上映日:2024年11月 埼玉会館
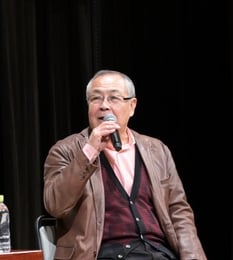
ゲスト:小野武彦さん(当作品主演俳優)
2024年11月19日「シェアの法則」のアフタートークを開催しました。
ゲストは主演の小野武彦さん。「踊る大捜査線」シリーズでのスリーアミーゴス、「科捜研の女」でも長くレギュラー出演をされるお馴染みの役者さん。「シェアの法則」は芸歴57年にして初の映画主演作品でした。今回の上映会では小野さんの「この映画を観に集まってくれた大勢のお客さんにご挨拶させてもらいたい」と1回目上映後と、2回目の上映前にご登壇いただきました。
初主演の話が来たときは、率直にうれしかったと言います。また主役と端役の違いについて、カメラはもちろん共演の役者さんの演技など、すべてが主役を中心に回っていくという醍醐味を味わったそうです。
「シェアの法則」はもともと劇団青年座の芝居用に岩瀬顕子さんが書かれた作品で、映画版として小野さんが主演を演じた作品です。群像劇であり出演者にも舞台経験者が多かったため、撮影の現場でも制作者や出演者も意見を出し合い、一緒に作り上げた作品として小野さんも大変お気に入り。この映画が好評だったため、小野さん演じる春山秀夫(シェアハウスの大家)の一年後を追ったスピンオフ作品も作られたそうです。こちらの一般公開は未定だとか。
小野さんに作品の見どころを聞くと「脚本を書いた出演者でもある岩瀬さんが現場で言っていたことなんですが、シェアハウスを舞台にいろんな人との交流を描いています。これは現実社会で希薄になりつつあることですが、本来は国や地球もシェアハウスみたいなものであり、みんなで共同生活しているわけで、この作品で人との交流や思いやりを感じてもらえればうれしいですね」と語ってくれました。
第324回『ナポリの隣人』 ●上映日:2024年11月 彩の国さいたま芸術劇場

ゲスト:押場靖志さん(イタリア映画研究者)
2024年11月16日『ナポリの隣人』のアフターセミナーを開催しました。ゲストは、イタリア映画研究者の押場靖志さん。この作品の舞台となったナポリや監督のジャンニ・アメリオ等作品の背景を説明しながら、セリフや映像に隠されたこの作品の見どころやポイントについて熱く語っていただきました。
この作品は、いわゆる“行間を読む”ような作品です。主人公はイタリアナポリに住む年老いた弁護士のロレンツォ。妻には先立たれ、娘、息子とはあまりうまくいっていない様子。娘が何故父を許せないのか詳しい説明はありません。妻が亡くなった理由も息子とも仲違いをしているのかも説明がないまま話は進んでいきます。そして、一見人間嫌いのような主人公の隣にこども2人を連れた問題を抱えた若い夫婦が越してきて、仲良く疑似家族のようになっていくのです。彼が何故お隣さんを気に入ったのか…もちろんその説明もありません。押場さんはこの作品について語るとき、イタリア映画界の巨匠ロベルト・ロッセリーニ監督の“大事なのは証明することではなく,ただ示すこと”というフレーズを繰り返しました。
押場さんによれば、作品に隠されている意味、例えば、ロレンツォが階段を上って帰宅するシーンでは、イタリアの建物では上階は富裕層が住むようになっているので、主人公は弁護士であり“金持ち”を意味しているということ、父を嫌う娘は弁護士ではないが、裁判所で通訳の仕事をしていて父の仕事に近い空間に身を置いていること等を説明。そして最後まで娘は父を見放すことができずにいて最後はそれを象徴するかのようなシーンで終わるのも、その直前の裁判所の父と娘のシーンに意味が隠されているということ等(押場さん曰くイタリアの裁判所を知っているとわかるそうです)、疑問符でいっぱいだった私たちに絶妙な話術でイタリア映画・文化の面白さを教えてくれました。
イタリア映画研究者であり、イタリア文化にも詳しい押場さんは全身を使ってこの作品の楽しみ方を解説してくださったおかげで、イベント終了後も来場者から次々と質問が飛び交い、久しぶりにゲストを囲んで質疑応答も行われました。この作品の面白さだけでなく、ゲストの魅力を十分に堪能できるアフターセミナーとなりました。
第323回『フォーリング』 ●上映日:2024年10月 彩の国さいたま芸術劇場

ゲスト:菊池友宏さん(理学療法士・NPO法人Remind副代表)
10月26日(土)「フォーリング50年間の想い出」アフターセミナーを開催しました。
今回は大宮区で「まちの保健室」を運営するなど医療と地域の架け橋になるべく活動されているNPO法人ReMind副代表であり、理学療法士の菊池友宏さんをゲストにお迎えしました。
菊池さんは介護施設や病院等で老齢期のリハビリ業務を経験後現在はフリーランスで様々な活動をされています。
まずお話下さったのは「認知症」の定義とはいったい何か?そこに表れる症状とは?難しい用語をひとつひとつ分かり易く説明して下さいました。「認知症」はあくまで症状の事で様々な病気が引き金になって起こるもの。認知機能が低下して社会生活に支障をきたした状態をさすので、この「社会生活に支障をきたしているか」が鍵となります。
様々な病気により出現する認知症ですが、はっきりした原因は未だ不明。ただ生活習慣病と呼ばれるものを基礎疾患としてもっている方は発症しやすいのでそれらを予防する事で一定の効果が期待できるそうです。
また早期に発見できると治療が可能な場合もあるというMCI(軽度認知障害)についてチェック項目などをご紹介下さいました。この時点で医師に相談できると良いですね。
認知症を遠ざけるために大切な事として会場では理学療法士さんらしく体操を交えて「適度な運動」と「脳トレ」の方法を皆さんと実践してみました。
一番心強かったのは最後に「認知症になっても大丈夫!」と思える準備について具体的に例をあげて下さったこと。近しい人と自分の事を話しておく、身近なサービスを調べておく、人との繋がりを大切に。将来の自分の為に今できることは色々ありそうですね。まずは一つでも始めてみませんか?
第322回『お父さんと伊藤さん』 ●上映日:2024年10月 蕨市民会館
第321回『英雄の証明』 ●上映日:2024年10月 埼玉会館
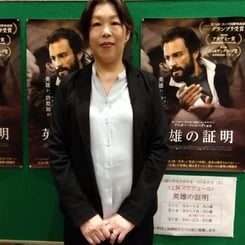
ゲスト:佐野光子さん(アラブ映画研究者)
テーマ:中東・イスラーム世界とSNS
2024年10月8日『英雄の証明』のアフターセミナーを開催しました。
この作品は、主人公の囚人ラヒムの婚約者が金貨を拾ったことで、主人公やその家族親類が騒動に巻き込まれていく姿を描いています。そしてその騒動に大きな役割を果たすのがSNSです。
佐野さんは、先ず、この作品の背景となるイラン社会の借金の保証人制度や刑務所の休暇制度について説明。主人公(債務者)は、彼の借金を肩代わりした保証人(元義父)に訴えられて刑務所に入ることとなったことや、軽犯罪の囚人は、申請すれば休暇を取って刑務所の外に出ることができること等をお話してくれました。
イランでは、2013年頃からスマートフォンの普及が始まり、SNS等で手軽に海外の情報を得やすくなったそうです。同時に政府の情報統制をかいくぐるための工夫等も生まれたとのこと。イランでの反体制デモや抗議活動が活発になった背景には、このようなスマホやSNSの普及があるようでした。その例として、2018年に生まれた「MosqueMeToo運動」(パキスタンのムスリム女性が巡礼中に性的虐待を受けたことをFacebookで告発が発端)や、“アラブの春”(2010~2012)のデモ等の抗議活動がFacebook等で呼びかけられたことについて解説していただきました。
後半は、現在緊迫する中東情勢についてのお話でした。佐野さんは第二次レバノン戦争(2006.7/12~8/14停戦)の頃現地に滞在していた経験があり、ヒズボラ(レバノンのイスラム教シーア派組織)について、また当時から現在まで緊張状態が続く中東情勢とその背景について説明。最後に、当時戦地で作られたビデオレターを流し、SNSが未発達の頃に映像をどのように広めていったかその苦労についてお話されました。そのビデオレターは、完成後にDVDにコピーし、プライベートボートで脱出するレバノン映画人にDVDを託しパリ・アラブ世界研究所に届けられ、その直後に開幕したパリ・アラブ映画ビエンナーレ(アラブ映画祭)で流すことができたそうです。当時はFacebook等も始まったばかりの頃で、戦時下で停電とネット障害もあり、そのような中DVDをリレー方式で届け世界に発信できるようになったとのことでした。
第320回『フィッシャーマンズソング』 ●上映日:2024年9月 彩の国さいたま芸術劇場
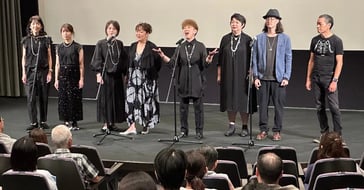
ゲスト:GTゴスペルクワイヤ
2024年9月14日「フィッシャーマンズソング・コーンウォールから愛を込めて」上映終了後、ゴスペルのアフターライブを開催しました。
ゴスペルの先生と生徒さんたちのグループで楽しい歌声を3曲披露してくれました。
M1 this little light of mine
M2 Joyful , joyful
M3 Souled out
第319回『ミス・マルクス』 ●上映日:2024年9月 埼玉会館

ゲスト:小田原琳さん(東京外語大学教授/イタリア史・ジェンダー史専門)
2024年9月10日『ミス・マルクス』のアフターセミナーを開催しました。
この作品は、思想家カール・マルクスの末娘エレノア・マルクスの生涯を描いた作品です。エレノアは、思想家の父の影響を受けて若い時から父の秘書などを務めながら女性の権利や子どもの保護等を訴えた活動家でした。一方で、私生活では、劇作家で社会主義者のエドワード・エイヴリング、という浪費家で“女癖の悪い”パートナーとの生活を自ら選び翻弄され続けるという、一見矛盾に満ちた生涯を送った女性でもあります。
小田原さんはまず、この作品、エレノアの生きた時代の歴史的背景を説明。「“平等”の概念」について“自由主義”と“社会主義”の「平等」の違い、社会主義思想の世界的な広がりについてお話されました。「自由主義の“平等”は、自由な競争の結果、格差が生まれても仕方ない。社会主義の“平等”は、ある程度社会をコントロールし、富を平等に分配すること。競争ではなく協力することが大切」とのことです。
そのような時代にエレノアは、女性の解放や子どもの保護等を訴え活動していました。18世紀末から始まった軽工業を中心とした「第一次産業革命」により、女性や子どもが安い労働力として従事していたことも大きな理由です。また、この時代における社会主義での「女性解放」“男女の不平等の解消よりも階級問題の解決が先”という考え方もこの時代に生まれたようです。
とはいえ、所謂“だめんず”のセンパイであると同時に女性権利の活動家であるエレノアについて、時代を超えて私たちは何を知り学ぶことができるのでしょうか。小田原さんによれば、過去には多くの名もなき女性たちが平等な社会実現のために活動してきた、という事実とそれを再発見する動きがあり、映画の中でも増えているとのこと。エレノアのような社会主義の理論家であり実践家であり、と同時に矛盾に満ちた姿は、歴史研究家では描けない魅力というようなお話をされていました。授業や歴史書の中ではなかなか知ることのできない過去の女性の生き方について、このような映画等によって現代の私たちは知ることができるのかもしれません。
-
アーカイブ:詳細の上映会 年を選ぶ [年]
-
アーカイブ
トップ -
前へ
. -
2025
. - 2023
-2024 -
2021
-2022 -
2018
-2020 -
2015
-2017 -
2012
-2014 -
2009
-2011 -
2005
-2008 -
次へ
.
